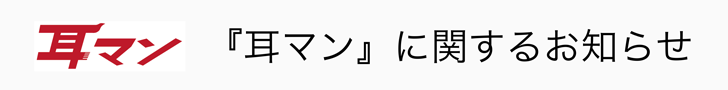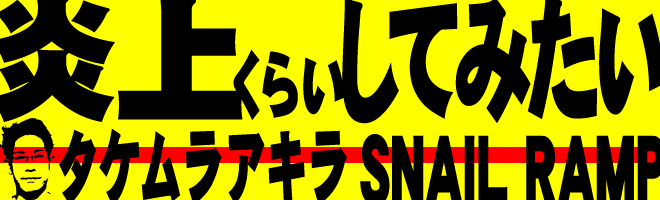「初のアルバムツアー~SNAIL RAMPの作り方・36」~タケムラ アキラ『炎上くらいしてみたい』
1990年代後半から2000年代のバンドシーンを牽引したSNAIL RAMPのフロントマンであり、キックボクシングで日本チャンピオンにまで上り詰めたタケムラ アキラが書きたいことを超ダラダラ綴っていく新連載!
1998年8月にセカンドアルバム『Mr.GOOD MORNING!』をリリースしたSNAIL RAMPは、程なくしてツアーに出た気がする。それまでも地方でライブをやったりサポートで全国ツアーを回ったことはあったが、自分たちがメインでの全国ツアーは初めてだった。
この1998年という年は日本のSKA PUNK、SKA COREシーンにおいては重要な年で、夏には東京(日比谷野外音楽堂)と大阪(大阪城野外音楽堂)で『SKA OF IT ALL』という一大イベントが行われ、両会場ともに満員。このシーンが盛り上がっていることをわかりやすく可視化できたイベントだった。
ちなみに前年1997年のゴールデンウィークあたりには、この前身イベントが渋谷NHKホール横のフリースペースで行われたのだが、予想以上の人が集まったうえに演奏の騒音苦情がかなり多かったようで、イベントはたびたび中断。おまけに中断、再開などイベントの進行を仕切る会社の人間が強権的でもあり、現場の雰囲気は一時騒然。1歩間違えば暴力的な騒乱状態に発展しそうな場面もあった。
そんななかでもSNAIL RAMPは何とかライブをすることができたが、確か1〜2個あとのバンドはライブ途中で中断させられ、イベント自体そのまま中止・解散となってしまう、苦い思い出となるイベントとなった。
なおこのイベントにはコカコーラ社がスポンサーにつき、ドリンクは飲み放題だったが、進行を仕切るその強権的な人間がコカコーラの赤いスポンサージャケットを着ていたこともあり、「は? コカコーラふざけんなよ」的な感じにもなり、その怒りで書いた曲が『THE DAY WAS NOT FINE』で、セカンドアルバムにも収録されている。
話をセカンドアルバムのツアーに戻そう。確か1発目が札幌、そこから青森、秋田と下ってくるスケジュールだったので、札幌行きも飛行機ではなく機材車にメンバー3人(石丸、米田、竹村)とマネージャーのテツラーノの計4人で北上。
仙台だか青森からフェリーに乗り、初めての北海道に上陸した。お客さんが来てくれるのかもわからない状態だったが、対バンのおかげもありライブハウスは7〜8割の入り。いい感じでライブを終えて、対バンしてくれた地元のバンドたちと楽しみな打ち上げへ。打ち上げもさすがは北海道、何てことはない居酒屋なのに出てくる料理がすべからく美味い。おかげで打ち上げも盛り上がり、ホテルのロビーに帰ってきたのが夜中の3時くらいだったか。
俺たちは東京から移動してきた疲れ、ライブで全力を出し切った心地よい疲労感、そして打ち上げでハシャギ、「あ〜、今日はぐっすり寝て、また明日のライブもガツンといくぞ。とりあえずメチャクチャ寝てやる!」状態。そこでマネージャーのテツラーノが、翌日の出発時間の発表。
テツラーノ「明日のライブは青森ね、函館からフェリーで行くから。ちょっと遠いなー。えーと、明日の集合は……このロビーに午前4時半ね」
俺ら「えっ!」
あの日の俺たちは有り得ないくらい疲れてて、32年経った今でもあの疲労感を思い出せるくらいなのだが、その俺らに「1時間半後の出発」を言い渡したマネージャー・テツラーノ。事前に札幌→青森の行程時間を調べてなかったのかな。いや、調べてはあったのかもしれないが、打ち上げが楽しくてテツラーノも「明日の移動とか、どうでもいっか!」みたいになっちゃったのかな。
文句を言っても仕方ないので、重い体で重いカバンを引きづりながらホテルの部屋に。とりあえずシャワーは浴びたけど、出発はもう1時間後。意識がボーッとするほど眠かったけど、寝てしまったら絶対に起きられない自信があったので、寝巻きではなく翌日の服を着て、念の為に携帯のアラームもセットしてから部屋の電気も点けっぱなしでベッドの上で体を伸ばした。
すると10秒後くらいに、アラームが意識の遠くで鳴っていることに気づいた。「あ、アラームのセット時間を間違えたか」と思って確認したら、しっかりと朝4時20分。寝るつもりなんかなかったのにマジで一瞬で寝てしまったらしい。でも行かねばならぬ。なんかフラフラするけど、無理矢理にホテルの部屋を出てエレベーターでロビーに。そこにはメンバーの石丸と米田、そしてテツラーノが無言すぎるくらいの無言でソファにヘタり込んでいて、全員が2億円の借金を抱えているような顔をしていた。
「……行くよ」
テツラーノの28歳女性とは思えぬ低いデス声に促され、俺たちは真っ暗なロビーを抜け機材車に押し込められた。ツアー初日を終えただけなのに「こんなに大変なら、ツアーとかそんなしなくてもいいかな……」などと考えながら、機材車は真っ暗な道を函館港へむけてひた走った。もちろん車内は全員無言だった。