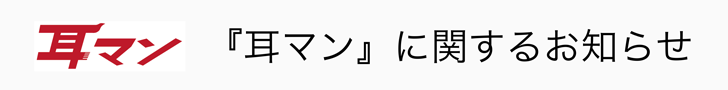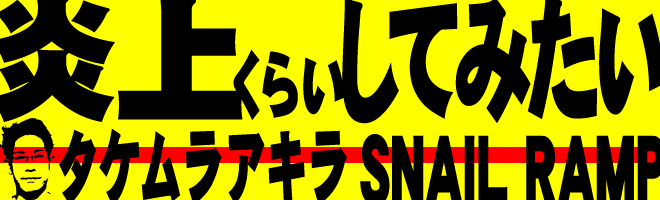「青森の打ち上げでくっそ盛り上がった翌日の秋田ライブ・中編~SNAIL RAMPの作り方・40」~タケムラ アキラ『炎上くらいしてみたい』
1990年代後半から2000年代のバンドシーンを牽引したSNAIL RAMPのフロントマンであり、キックボクシングで日本チャンピオンにまで上り詰めたタケムラ アキラが書きたいことを超ダラダラ綴っていく新連載!
前日の青森マグネットでの打ち上げで散々騒ぎ、お開きになってからもホテルで二次会、ほぼ寝ずに秋田へ移動した俺。移動の車中は瞬間寝落ちからの爆睡だったものの、起きたらまったく声がでなかった事態に顔面蒼白。しかししかし、俺には耳鼻咽喉科でとっておきの注射を打つという秘策があった。
以前にも喉の調子が悪かったときに絶大な効果をもたらしたあの注射。俺はリハ終わりで医院を探し、そこに文字どおり飛び込んだ。
「(すみません……声が出なくて)」
「え? 何ですか?」
「(声が、出ない、んです!)」
「ホントだ。出てないわね」
だから出ないって言ってるじゃん!!というやり取りを受け付けのおばちゃんとしつつ、待合室で診察を待つ。座ってみて気がついたが、なかなか年代物の医院のようだ。
「秋田の地域医療に携わって数十年、地元の人に頼りにされ、愛されてきた医院なんだろうなぁ……」と妙な感慨にふけってみたが、待合室には俺だけ。柱にかかっている時計の音が響きわたるほどに「しーん」とした医院。「あれ? これ愛されてないんじゃ……?」と持ち始めた疑いをかき消すように「竹村さん、診察室にどうぞ」と秋田訛りで呼ばれた。
そそくさと診察に入るとそこにはお世辞にも初老とは言えない、おじいちゃんが座っていた。
「どうしました?」
「(声が出なくなっちゃって)」
「え?」
「(声が出ません)」
「え?」
「(声が……)」
と言った瞬間、「声が出ないんですって!!」と受付からおばちゃんの声が医院中に響いた。
「あぁ、そう。だったらそう言ってね」
「(言いました……何度も……涙)」
おじいちゃん先生は耳が遠かった。耳の遠い耳鼻科の先生に会うのはこれを最初で最後にしたいが、そこに声の出ない患者が来るとは何ともまぁ皮肉な組み合わせだ。
「(騒ぎすぎて声が出なくなっちゃったんですが、これからライブで歌わなくてはいけないんです。前に別の耳鼻科で注射を打ってもらって良くなったので、それをお願いできますか?)」
「注射? 何の注射を打ったの?」
「(何の……?)」
言われてみて気づいたが、確かに俺は以前に打ったその注射が何だったのかまったく理解していなかった。でも病院でそれを伝えれば、医者同士はわかるもんだろうと勝手に思い込んでいた。
「(わからないんですが、打ってしばらくすると声が出るようになりました。それを打ってもらいたいんです)」
「うーん、でもそれが何かわからないなぁ」
おじいちゃん先生は困ったような顔をしていた。
「(じゃあ、先生がいいと思う治療をお願いします)」と告げた。そうすると「じゃあ、まずはこれをやって」と耳鼻咽喉科でよくやる吸入器のスペースに通された。そして「これを口と鼻にあてがって、吸ってて」と酸素吸入マスクのようなアレを渡された。
その頃でもほとんどの耳鼻咽喉科では、フニャフニャとした柔らかいシリコンのような素材のマスクだったはずだが、おじいちゃん先生が手渡してきたのはガッチガチのガラス製だった。「太平洋戦争中の暮らし展」とかで展示されてそうなガラス製のマスクをあてがって吸入を始めたが、どうも勝手が違う。
薬効成分を含んだ細かい霧状の水分がシューッと蒸気のように出てきて、俺は気持ちよくそれを吸い込む。気づくと声も出るようなり今晩のライブも絶好調……そんなはずが、マスクのなかでは豪雨のような薬効水分が俺に向かってただただ噴出、直撃していた。しかもそのガラス製マスクは顔のカーブにまったくフィットしないため、噴出する豪雨が俺の頬、眼、おでこ、首回りにまで飛び散っている。
「江戸時代とかの水責めって拷問、これの上位互換なんだろうな」と思いながら、ひたすらその噴き出る水分を少しでも体内に取り込もうとがんばったが、全体の4割はマスク外に飛び散り俺の体や服をただ濡らしていく。
(後編に続く)