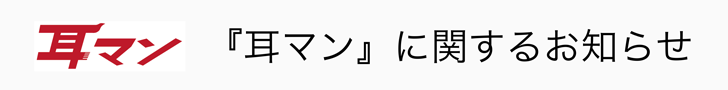【80年代当時のレアエピソードも】ジグ・ジグ・スパトニック・エレクトロニック来日! 掟ポルシェによる豪華1万字超えインタビュー
祝・来日♡ ジグジグのマーティンに掟ポルシェがインタビュー!
SFチックな世界観や近未来的なサウンド、唯一無二の独創的なファッションを武器に、1980年代にムーブメントを巻き起こしたイギリスのニューウェイヴバンド、ジグ・ジグ・スパトニック(以下、SSS)。2023年11月、同バンドのマーティン・ディグヴィル(ボーカル)が“ジグ・ジグ・スパトニック・エレクトロニック(以下、SSSE)”として来日し、東京・大阪でライブを開催。そんななか、日本屈指のジグジグマニアとしてお馴染み(!?)のミュージシャン・掟ポルシェ(ロマンポルシェ。)をインタビュアーに迎えてインタビューを敢行! 1980年代当時のエピソードから現在の活動に至るまで、たっぷりと語っていただきました。当サイト『耳マン』独占のレア情報満載インタビューを、どうぞお楽しみください!!
マーティンと掟は “ナイスなキス”を交わした2002年以来の再会!?
――久々にお会いできて感激です! ここのところは世界中のロックフェスを飛び回っていてお忙しそうですね。
マーティン・ディグヴィル(以下、マーティン):今はヨーロッパでたくさんプレイしているよ。ドイツやイタリアで開催された大規模なゴシックのフェスでもプレイしたけど、イギリスではそんなにプレイしていないのが現状だね。ヨーロッパ大陸のほうでプレイすることが多くて、そっちではナイスなクラブからビッグなフェスまでいつも楽しんでいる。でも一度に5、6回プレイするようなツアーとしてまわることはないかな。毎月から数ヶ月に1回ショーをプレイしに飛行機に乗って行き、終わればイギリスに帰ってくるような感じだね。
――2002年の初来日公演では私のバンド、ロマンポルシェ。がサポートアクトを務めさせていただきました! あの、覚えていらっしゃいますか?
マーティン:あのとき一緒にプレイしたの? あまりにも昔のことだから覚えていなくてね(笑)。時差ボケもあるなかでテレビ用のインタビューも受けていたので、眠れるときに眠れるようにウィスキーをたくさん飲んでいたからね。こっちの深夜12時でもイギリスでは普通に出掛けるような時間なのに、翌朝はプレス対応のために早く起きなきゃならないみたいな感じだったから。
――そうですか……だったらこれも覚えていないかもしれませんが、あなたからのリクエストで大阪と東京のショーの合間のオフ日に新宿2丁目にアテンドさせていただいたんですよ。でも、そこのお店にお好みの男性がいなかったようで、結局私がキスされました(笑)。
マーティン:そんなことしたの? 良かったでしょ? ナイスなキスだったでしょ(笑)?
――あんな高等テクニックを伴ったキスは初めてでした。ガッチリ閉じた私の唇にコークスクリュー状に舌をこじ入れて、歯の上で高速ベロ回転されまして、本当にすごかったです(笑)。
マーティン:オー、イェー(笑)♡ 一緒にゲイクラブに行ったんだよね?
――そうです。でもなぜか私があなたにキスされました(笑)。
マーティン:多分、君のことを気に入ったからなのだろうね!
――私自身ノンケですが、非常に光栄でございます! SSSEの来日としては今回が初となりますよね。
マーティン:そうね、オリジナルバンドではない形としては初めてだね。
――2010年にSSSEを名乗って以降、今回同行したメンバーのヨハン・ワイデマンさんと一緒に音楽活動をされていますよね。
マーティン:そのとおり。彼は作曲には関与していないけど、ツアーに一緒に出てキーボードをプレイしてくれてね。そして彼は僕の夫でもある。家族でもあるからバンド活動もやりやすいよね。
――ヨハンさんのX(旧Twitter)のトップ画面があなたと見つめ合っている画像だったので、多分そういうご関係だとは思ってました。彼とはどのように出会ったのですか?
マーティン:ロンドンのソーホーにあるトレンディーなゲイバーで会って話したのが最初。翌日、スプートニクウォッカという酒造メーカーの催し物で、ロンドンの蝋人形博物館『マダム・タッソー』の中の宇宙船をモチーフにした場所でちょっとしたライヴを僕がやることになっていたから、観においでと誘ったんだ。それから僕たちは一緒に過ごしているよ。それが2004年のことで、2010年にはヨハンの出身である南アフリカで結婚したんだ。彼はプレトリアという都市の出身で、もちろん現在ではイギリスの住民権を持っているよ。
――SSSEになってから今まで、コンスタントに作品をリリースされていますよね。SSSの名曲の新録バージョンとオリジナル曲も同時に収録されていますが、それらもすべてあなたとヨハンさんで製作されているのでしょうか?
マーティン:ヨハンとだけというわけではなく、曲のプログラミングはロイド・プライスというミュージシャンが担当していてね。2013年にリリースしたアルバム『エレクトニック DNA 2049~もう一度見せびらかしましょう~』も彼によるもの。SSSEの製作の流れとしては、まず僕がすべての曲を書いてざっくりプログラムし、アレンジメントとメロディーを考え、仮のボーカルも作ってからプログラマーにデータを渡す。するとすべて綺麗にプログラムし直して文句のつけようがないモダンなサウンドにしてくれるんだ。やっぱりハイテクな機材の操作に長けた人に任せたほうが早いことってあるからね。それで僕のところに戻されてきた音源ファイルに最終的なボーカルトラックを入れて、イギリスとドイツにいるSSSEのギタリストたちに送ってギターのパートを入れてもらい、最終的なミキシングを行って完成する。以前SSSをやっていた頃にはメンバー全員揃ってスタジオに入るっていうオールドスクールなレコーディング方法でやっていたけど、最近はWAVファイルを送り合うってやり方が主流だよね。僕はいつもさまざまなミュージシャンたちを使っていて、バラエティー豊かなアイディアのインプットを音楽に込めたいんだ。ほかの人と作業するっていうのは僕にとって良いことだと思うしね。
「SSSはカッコよくて未来的でSF版ニューヨーク・ドールズにしなくちゃダメだと思っていた」
――オリジナルのSSSの頃からあなたたちのイメージは近未来的でしたが、衣装を含めたファッションデザインはすべてマーティンさんによるものでしょうか?
マーティン:SSSのビジュアルに関しては全部僕が考えた。その昔僕たちはケンジントン・マーケットというとてもトレンディーな場所に『YA YA』というショップを構えていて、初期SSSでダブエフェクトを担当していたヤナ・ヤーヤーと私がデザインを担当していた。トニー(・ジェイムス/SSSのベース)とはそこに彼が服を買いに来たことがきっかけで出会ったんだ。当時の彼はレザージャケットにトップハットといった典型的なロックンロールファッションでつまらない格好をしていて、「そういうのは受け入れられないね」と言ってやったよ。僕はね、SSSはカッコよくて未来的でSF版ニューヨーク・ドールズにしなくちゃダメだと思っていた。私のインスピレーションの源はデヴィッド・ボウイとロックと音楽で、かなりワイルドなデザインを求めてたくさんの先人のアイディアを拝借し、それらをさらに磨き上げてオリジナルなものを生み出していた。服のデザインに関して僕が生み出したテクニックで、“ストリンギー・フィンガーズ”っていうのがあってね。ストレッチ性のあるジャージ生地を切り刻みそれらを紐のように結び付けてヒラヒラとさせ、それでいくつもの服を作っていった。ロンドンで大きなファッションショーを行ったけどかなりクールだったね。服を切り刻むっていうテクニックは今でもポピュラーだけど、これは僕たちが考え出したものなんだ。僕はエルヴィス・プレスリーのSF版になりたかったから。
――まさにELVIS1990ですね! SSSはそのファッションも音楽も革命的でしたが、その独自の宇宙的なサウンドに至った背景にはザ・クラッシュのメンバーの尽力があったと聞いています。
マーティン:そのとおりだよ。ザ・クラッシュのミック・ジョーンズ(ギター)がシーケンシャル・サーキットのPro-Oneというアナログシンセを僕たちにくれて、あれは当時かなり時代を先取りしたエレクトロニックサウンドだった。ファーストアルバム『ラヴ・ミサイル』(1986年/原題:Flaunt It)では全編に渡って使用したよ。これとローランドのドラムマシンTR-808がスパトニックのサウンドとなり、生のベースなんてまったく入っていなかったんだ(※ドラマー加入前の初期SSSでは、簡単なシーケンサーを持つPro-OneのGATE/CLK INにTR-808のクロックを入れてトリガーさせて同期演奏し、その上にニールXのギターとエコー処理したマーティンのボーカルを乗せたSSSサウンドがすでに完成していた。これら初期のデモレコーディング曲は後に『ザ・ファースト・ジェネレーション』というタイトルでリリースされている)。それからしばらくしてドラマーがふたりやってきた。でも彼らは(見た目だけで選んだメンバーだったため)ドラムをまったく叩いたことがなかったんで、最初の2年はドラムの叩き方から僕らは教えたよ。ふたりにはシモンズのエレクトロニックドラムのキットを使ってもらった。エレクトロニックドラムが素晴らしかったのは、ライブでもアルバムとまったく同じようなサウンドでプレイすることができたことなんだ。多くのバンドってレコーディングとライブを聴き比べるとかなり違っているからね。それに僕は生のドラムが嫌いでね。かなりオールドファッションに思えたしね。
――『ラヴ・ミサイル』制作時にもいろいろおもしろいことがあったとか。
マーティン:『ラヴ・ミサイル』はジョルジオ・モロダー(※イタリアの音楽プロデューサー)がプロデュースをしてくれたのだけど、レコーディングの場にロサンゼルスの売春婦たちを連れて来ていた。毛皮のコートだけを纏ったモデルみたいに綺麗な女たちがやってきて、ジョルジオは「1時間後に戻ってくるから」といって一旦抜けることもあったよ(笑)。彼はなかなかおもしろい人だったね。
――ジョルジオ・モロダーちょっといい話ありがとうございます! SSSのデビューは音楽ファンの間でホットな話題となりました。その理由のひとつは400万ポンドと噂された高額な契約金にありましたよね。
マーティン:それは実はプレスによって広められたデマなんだよね。当時まだ創刊したばかりの音楽誌『NME(ニュー・ミュージカル・エクスプレス)』の記者が僕たちにインタビューしてくれて、表紙を飾ったことがあった。そのときの見出しが「あなたはこのクズどもに400万ポンドも払うのか?」というもので、僕たちのことをクソ扱いして酷くコキおろしてくれたよ。だからあれはジャーナリストが作ったもので、僕たちは音楽を知ろうともしないプレスから結構酷く扱われてきたんだ。音楽以外のゴシップネタ、それこそドラッグとかパーティーについてばかり取り上げられ、ファーストアルバムは完全に音楽的には見下されていたね。
――もちろん実際の契約金が35万ポンドだったことも知っています。それらは一体何に使われたのでしょうか?
マーティン:ビデオの制作なんかに使ってしまったよ。それからプレスの対応や身のまわりのことをこなすためにスタッフをたくさん雇わなければならなくなり、次第に普通のバンドから大きな企業みたいになっていったんだ。あまりにも規模が大きくなって音楽が主体ではなくなり、一般大衆に向けてひたすら売るための装置になってしまった。バンドがあるべき姿や素晴らしさといったもののすべてを失ってしまったんだ。レコード会社が気にしたのはルックスとそこにリンクしたサウンドだけで、ペット・ショップ・ボーイズやプリンスもそうだったし、僕の多くの友人たちだって同じ境遇にいたこともあった。今では音楽産業は当時とまったく異なっているとはいえ、テイラー・スウィフトみたいに自身の著作権をすべて取り上げられてしまうようなことだって起きている。僕たちはそんなに大金を得ることはなく、ほとんどがEMIに奪われていくような状況だったよ。本当にどうしようもない状況だったし、レコード会社は誰がプロデュースを行うのかにまで口を出していた。僕は自分にとってのヒーローだったデヴィッド・ボウイによるプロデュースを熱望していた。彼はロックンロールでありスペースマンでもあったから。ニールX(SSSのギター)はプリンスをプロデューサーに迎えたがっていた。もちろん僕もプリンスを愛しているし、当時最先端で音楽界のトップに君臨した存在だから彼にプロデュースしてもらえるならと僕も願っていた。だけど僕らのバンドを危ない奴らだと言われて断られてしまったんだよね。「オー、ノー、僕にはデンジャラス過ぎる!」ってね(笑)。そこでEMIのお偉いさんが「ジョルジオ・モロダーにやらせよう」って言ったんだ。
――それでジョルジオ・モロダーにプロデューサーが決まって。
マーティン:まず、彼のベルリンのスタジオに行ってデモを聴いてもらったら「『ラヴ・ミサイル F1-11』は良いんじゃないかな」と言われて、この曲が僕らの最初のリリースとなったんだ。世界中で大ヒットとなりほかにも数曲ヒットしたけど、彼が施したサウンドプロダクションについては正直なところ満足いってなくてね。ドナ・サマーのようなディスコとロックンロールをフュージョンさせるというアイディアは気に入っていたし、モロダーはドナ・サマーを生み出したのだから必然だったとも思っている。だけどロックンロールが僕には足りなかったんだ。軽くてタフさやハードコアさが足りなくて、僕的にはイマイチだった。プロダクションはグレイトだったしミックスも申し分はなかったけど、僕としてはもっとハードなエレクトリックサウンドにさせたかった。大きく脈打つようなベースやエレクトロニックなドラム、その他さまざまなものが欲しかったんだ。ヘヴィーメタルっぽい方向に向かいながらもエレクトロニックさを求めてジョルジオ・モロダーにオファーした、というところだね。当初レコード会社は僕らにほとんど制作費を支払うことはなかったんだけど、最初のシングルが売れまくると方針を撤回して予算を回してくれるようになり、僕らはビデオのプロダクションなどに大金を注ぎ込むようになっていったよ。
――あなたはバンドを始める前から派手な見た目もあってすでに有名人でしたよね。あまりにも奇抜なファッションでカッコいいのでカルチャー誌『i-Dマガジン』のグラビアを飾ったこともあったとか。
マーティン:当時僕はファッションデザイナーになりたいと思っていた。その道で成功したいと思っていたけど、正統なファッションデザインについて一度も勉強したことがなかった。それでもあるときクリスマスに友人がミシンをプレゼントしてくれて、自分の頭のなかに思い描いた服を購入できる場所がどこにもなかったから、自分で服を作り始めたんだ。あの頃クラブやライブハウスに行くと、「そのカッコ、最高だね! どこで手に入れたの?」と頻繁に尋ねられていた。それ以来自分で作った服をプライベートな形で友人に譲るようになり、それが広まっていって多くの人が僕が作った服を着るようになっていった。その規模があまりにも大きくなっていったので、イングランドで2番目に大きな街であるバーミンガムでショップを開店して販売を開始したんだ。その後バーミンガムからロンドンのケンジントン・マーケットに移転した。
――それが先述の『YA YA』で、お店の服と一緒にオーナーのあなたが『i-Dマガジン』のグラビアを飾ったと。
マーティン:そのとおりだよ。
――ジグ・ジグ・スパトニックを始める以前、ヴィサージのボーカリストのスティーヴ・ストレンジがオーガナイザーを務めていたクラブ・ブリッツに通っていたと聞きました。
マーティン:彼はよき友で、クラブ・ブリッツは音楽業界やファッションデザイナー、そこでデビューを目指す人たちなどフリーキーな人たちが集まる場所だった。アンダーグラウンドなクラブシーンを代表する存在って感じだったけど、数年経ったら尖った感じを失ってつまらない場所になっていった。オープンしたての頃なんて選ばれた人しか中に入れなくて、ミック・ジャガーですら「僕たちはあなたが気に入らないので入店はお断りだ」って感じでかなり特別な場所だったのに、金に目が眩むようになって金さえ払えば誰でも入れるようになって雰囲気が変わっていった。フリーキーな人が来たらそれを嘲笑するような空気も生まれてきて、素晴らしいファッションや音楽を楽しむような場所じゃなくなっていった。何にでもいえることだけど、コマーシャルに走ると最終的にはダメになるよね。
1990年代、ボーイ・ジョージと同居していた頃のレアエピソード
――バーミンガム在住時代、あなたの家にはボーイ・ジョージが居候されていたことがありましたよね。
マーティン:うん、彼が「バーミンガムに移住したいんだ」と僕のショップにやってきたことがあった。それまで面識はなかったけど、彼は僕の居場所を調べてショップまでやってきて「仕事をもらえないか?」と言ってきた。「どうして僕のところで働きたいの?」と尋ねたら、「ロンドンのファッションシーンではかなり知られた存在になってしまってやりづらくなってきたから」って言ったんだ。彼はかなりおもしろい人だったし、僕らはウマが合ったので彼にショップでの仕事を与えることにした。僕はヴィクトリア調の大きな家に住んでいたので、「来たければ僕の家に上がり込んでくれて構わないよ」と伝えて、それで僕の家に住むことになった(※ボーイ・ジョージの自伝『Take It Like A Man』<1995年>によれば1979年の春に同居を開始)。でもあるとき、僕が値付けした素敵なドレスを彼が何倍もの値段で売っていたことを知ったんだ。僕のそのドレスを纏った女性にクラブで出会った際に「そのドレス似合っているわよ」と言うと、「結構高かったのだから、それは当然よ」と返された。「どういうこと?」と問いただすと、「130ポンドもしたのよ」と教えてくれた。ジョージに「あのドレスは30ポンドなのに、君は遥かに高い値段で売って差額をくすねていたの?」と問い詰めたよ(笑)。そんなこともあったけど僕らは本当に仲良くやれていて、あるときロンドンに行って一緒に住む場所を探してみないかということになった。僕は服の手直しの作業に追われて忙しかったので難色を示し、彼は「先に行ってしばらくお母さんと住むことにするよ。君は半年後くらいに落ち着いたら来てくれればいい」と言ってくれたけど実現することはなかったね。彼はロンドンに戻りクラブに出演するようになり、あとは歴史が知るとおりの成功を掴んでいったんだ。彼はもはや世界レベルのポップスターでありアイコンとなり、みんなと違う人やバイセクシャルの人たちのための道を切り拓いた。彼がい続けてくれたからこそ多くの人に意味をもたらし、ゲイの人たちも自信を得ることに繋がった。虐げられてきた人たちやゲイたちを勇気づける存在になっていったんだ。
――ジグ・ジグ・スパトニックは1989年と2003年に、2回の解散をされています。そして2003年の解散時にマーティンさんのスパトニック2とトニーさんとニールさんのジグ・ジグ・スパトニック・エレクトロニックへと分裂していったと記憶しています。当初あなたはスパトニック2を名乗っていましたが、いつの間にかあなたがジグ・ジグ・スパトニック・エレクトロニックの方を名乗るようになりました。どのような経緯があったのでしょうか?
マーティン:2003年の解散のとき、トニーは否定しているけど彼は僕をクビにしてギタリストのニールXをシンガーにさせたいと考えていた。ニールはボーカルとギターを同時にできなかったからかなり馬鹿げていて、やらせてみたらとにかく酷かった。トニーは弁護士を雇い、「君はジグ・ジグ・スパトニックの名前を使えない」と僕に言ってきた。「どうしてダメなんだ?」と尋ねたら「君はジグ・ジグ・スパトニックの名前の権利を有していない」と言ったんだ。でも僕は「そもそもこの名前って『ヘラルド・トリビューン』紙に載っていたロシアのアングラなギャングたちの名前だろ?」って言い返してやった。このギャングっていうのはマネーロンダリングや売春斡旋といったさまざまな悪事を働いていた集団だった。「このアングラな集団から名前をパクっているわけで、そもそも権利は君も僕も有しているわけではないだろう? 君の所有物でも権利物でもないのだから弁護士から僕に名前の使用をやめさせるような手紙を送らせるな!」と言ってやったんだ。それでも話はどんどん泥沼化していったけど、あっちが折れて「名前を使ったって構わないけど小文字にすること、しかもサイズは1センチ以下とすること」と言ってきた。「なんてバカなことを言っているんだ。ふざけるな、もうお前とは金輪際関わらない」と言ってやったよ。そこで僕はジグ・ジグ・スパトニックのあとに“エレクトロニック”とつけることにして、それ以来彼らは何も言わなくなっていった。“エレクトロニック”という言葉を付けたのは自分たちはエレクトロニックなバンドで、電子音が好きだということなんだ。オリジナルの名前を使いながらもそれとは少し違うバンドであることを表現し、あらゆる問題も回避していったんだ。
――そういった背景があったのですね。
マーティン:トニー・ジェイムスは結構ナルシスト気質なところがあって、自分が新たなマルコム・マクラーレンだと思い込むくらい自惚れていたことがあった。自分がすべてを手掛けていると思っていたようだったけど実際のところバンドの作曲にはほとんど関与していなくて、全部僕とニールXによるものだった。歌詞はすべて僕が書いていて、トニーは曲のタイトルを持ってくるとかその程度のことしかしなかった。彼は有名な映画からサンプリングしてくることがあって確かにそれらを曲中で僕らは使っていたけど、それはバンドのクリエイティヴな作業とは別のものだった。僕らのルックスや音楽に関して大した貢献はしていなくて、僕らは決裂して今も話をすることさえないんだ。
(※現在トニーとニールは「ジグ・ジグ・スパトニック」を名乗っているが、SSSとしてのライブ活動は特に行っていない。ニールXはマーク・アーモンドのバンドマスターも務めており、マークのコンサートにはニールが『ラブ・ミサイル F1-11』を歌うコーナーがある。逆にマーティンのジグ・ジグ・スパトニック・エレクトロニックは年に数回のライブを行うなど今も精力的に活動中)
「バンドをやることは自分にとって天職だって昔からわかっていたよ」
――SSSEについて、新作の構想もあるそうですね。カバーアルバムの予定もあるとか。
マーティン:来年リリース予定のカバーアルバムの製作に今取り掛かっているよ。日本でもリリースになるだろうし、テツ(2020年以降SSSEの日本盤をリリースし、今回の来日招聘元でもあるB.I.J.RECORDSのtetsu nclaren氏)はグレイトなスタッフチームやアニメのグラフィックアーティストたちとやり取りをしてくれていて非常に感服している。すべてをロンドンでレコーディングしたら日本に持って来てミックスをしてもらうかもしれない。カバーアルバムだけでなくニューアルバムの曲も同時に書いていて、これについても2014~2015年以降にキチンとしたものをリリースしていないから来年中にやりたいと思っているんだ。
――今でも世界中にジグ・ジグ・スパトニックを愛する人たちがいて、熱狂的なフォロワーたちがあちこちに存在しています。世界的に影響を与えるようなミュージシャンになることを少年時代のあなたは想像していましたか?
マーティン:そうだったと思うね。今になって振り返ると僕らが世の中に出てきたとき、ほかのバンドとはあまりにも異なっていたから、みんな新たな近未来的セックス・ピストルズが現れたと思っていた。ムーブメントを起こすようなバンドが生まれるときって「あれってすごいよね?」と考えるバンドがたくさんいて、そのスタイルをコピーしようとするものだ。セックス・ピストルズが出てきたときにパンクが始まり、キチンとプレイできないようなバンドがすぐにたくさん生まれた。当時はパンクとはそういったものが美徳とされていて、ステージに上がって暴れてくればよかったわけで、作曲だって適当なものが多かった。単に大きなノイズって感じで無秩序だった。それでいて社会に背くステートメントをして自分がなりたい姿になり、着たいものを着て着飾っていた。僕たちもそういったムーブメントになろうとしたけど、それは実現しなかったよ。僕らのスタイルをコピーしたバンドはいくつかいたけど、スパトニックの影響を感じるようなものを実際にその音楽のなかに感じられるようなバンドは後になるまで出てくることはなかった。あとファーストアルバムをリリースしたとき、トラックの間にロレアルといった大きなコングロマリット企業の広告を挟むなんてことを初めてやって、その数年後に同じようなことをするバンドも出始めたんだ。今でもスパトニックのイデオロギーを感じるバンドを耳にすることはあって、エレクトロニックなサウンドを用いてロックンロールをさらに押し進めた新たなサウンドを彼らは作り続けてくれている。未来を最もエレクトロニックな形で見せてくれているよ。
――最後の質問になりますが、子どもの頃になりたかったものは何でしたか?
マーティン:14歳の頃、すでに僕はゲイであることを自覚していた。学校でも変なカッコをしていて、テイラーをしていた叔父に学校の制服をすべて作ってもらっていた。ただみんなと違うという理由だけで学校でいじめを受けていたこともあったし、当時僕が住んでいた地域では髪の毛を赤く染めただけでもかなり変なことだと思われていた。僕はいつもデヴィッド・ボウイみたいになりたいと思っていて、彼は僕の幼少期に大きなインスピレーションを与えてくれていた。多くの人と自分は異なっていると感じることもあって、バンドを観に行くとオーディエンスの中で踊る友人たちの中からいつも僕は浮き立っていたので、後ろのほうでひっそりとしながら「いつか自分もステージに立ってパフォーマンスをするんだ」って思っていた。当時はブロンディー、イギー・ポップ、クランプス、ニューヨーク・ドールズといった素晴らしいバンドたちが活躍していた時代だったからね。そして当時の僕は歌えなかったけど、ただエンターテイナーになりたかったんだ。あるときトニーがニールと一緒に店にやってきて、「新しくバンドを組もうとしていて、シンガーを探している。君は歌えるか?」と言われた。僕は音を外さずにしっかりと歌えるわけではないけど「もちろん歌えるよ」と答えたね。初めてリハーサルに行ったとき、『ビー・バップ・ア・ルーラ』やエルヴィス・プレスリーやローリング・ストーンズの曲をカバーしたけど、僕の歌は音をかなり外して酷いものだったよ(笑)。独学で歌を学んでいったんだよね。彼らはこれらのカバー曲を録音していたんだ。あとから知ったのだけど週末にバーミンガムの店に赴くために僕がロンドンを離れている間、彼らは10人くらいのヴォーカリストたちをオーディションしていてそれを僕には黙っていたんだ。それを教えてくれたのはミック・ジョーンズで、彼は10人のシンガーたちがそれぞれ歌ったバージョンの曲を聴かされて「マーティンをシンガーにするべきだ」と言ってくれたらしいんだ。それが僕の声質、歌の届け方、センス、どれによるものだったのかはわからないけど彼がいなかったらバンドのシンガーになっていたか分からないよ。そして僕はずっと曲を書きたいと思っていて、その機会を得た僕はバンドのサウンドを作ると同時にトランスジェンダーといったトピックを扱った歌詞を書くようになったんだ。『シーズ・マイ・マン』『ラヴ・ミサイル F1-11』『アタリ・ベイビー』はスタジオでジョルジオ・モロダーとともに作っていって、僕はそれまでバンド活動をしたことがなかったにもかかわらずとても楽しかった。トニーとニールXはいくつかのバンドで活動していたけど、バンドが初めてだった僕にはレコーディングプロセスのすべてが斬新でロックンロールの世界に足を踏み入れたのは心地良かったんだ。バンドをやることは自分にとって天職だって昔からわかっていたよ。
(おわり)
<撮影:佐藤哲郎>
<通訳:トミー・モリー>