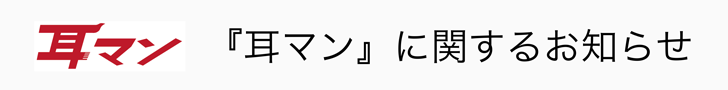【最終回】『BRADIOのファンキーハンター』【魅惑のカッティングギター&グルーヴ〜レイ・パーカーJr.編】
人気上昇中の若手ファンキーロックバンドBRADIOが、より“Funky!!”なバンドを目指すべくファンキーなヒト・コト・モノに出会いに行く連載!
『ゴーストバスターズ』でお馴染みの稀代のミュージシャン
まずレイ・パーカーJr.ってどんな人なの?と聞かれて、馴染みのある一番わかりやすい説明が「ゴーストバスターズの曲作った人」ってことだね! 1954年デトロイトに生まれギタリストとしてスティーヴィー・ワンダーとか数々のセッションに参加するんだけど10代の前半ぐらいではもうすでに業界トップクラスのスタジオミュージシャンになってたってんだからその実力は折り紙付き(しかもギター始めて猛特訓して1年でらしい!)。作曲やプロデュース、エンジニアにベース、キーボード、ドラムなどほとんどの楽器ができるマルチプレイヤーなんだけど、ギタリストとしての代名詞はやはりカッティングのギタースタイル! BRADIOでもそーいちが『きらめきDancin’』のイントロとかでやってる奏法の名手だ。1977年には自身が中心となってレイディオ(Raydio)というバンドをつくり、レイ・パーカーJr.&レイディオと名前を変えたりしながら1981年に解散するんだけど、その後もソロ活動やプロデューサーとして作曲家としてのキャリアを築いてく。『A Woman Needs Love (Just Like You Do)』はメロウな代表曲のひとつ!
今回は“セッション王”とも称されるほど数多くのビッグアーティストと共演しているギタリスト、ポール・ジャクソンJr.も一緒に来日! インタビューにはポールも参加してくれて、興奮度120%のスペシャルなセッションを浴びてきました!
貴秋:今日は貴重なお時間を割いてくださって、ありがとうございます!
レイ・パーカーJr.(以下RP):いやあ、来てくれてありがとう!
貴秋:僕らのバンドは、Bradioというんです。あなた方はA-Radioで、僕らはB-Radio。
ポール・ジャクソンJr.(以下PJ):ほんとか(笑)!
RP:スペリングは?
貴秋:「B-R-A-D-I-O」です。
PJ:ワカリマシタ。
RP:「B-R-A-Y-D-I-O」のほうがいいんじゃないの(笑)?
PJ:ワカリマセン(笑)!
貴秋:ハハハハ! 最初の質問です。これはインタビューするみなさんに聞いているんですが、僕のアフロは10点満点で何点ぐらいですか?
RP:昔のオレとほとんど同じじゃないか。10点満点だよ!
PJ:オレのアフロも似たような感じだったけれど、もう少し短かったな。でも、オレの幼なじみのアフロは「完璧」だった。彼はクシで髪の毛を立てた後、アフロ全体をスカーフで覆って、上から軽く叩いて全体の形を整えていたんだ。だから、今は7.5点しかあげられないけれど、スカーフで整えれば10点満点だ。
貴秋:それは知りませんでした。帰ったらやります!
PJ:よろしい!
貴秋:今日は、この取材が終わった後でステージを観させていただくんですが、どんなショウになるのか、ちょっとだけ教えてもらえますか。
PJ:ウーン、そうだな、オレたちのショウはリズムが正確で……。(隣のレイがiPadで自分の写真を探し出す)
RP:ほら、これは髪の毛が短かった頃の写真だよ。まだ15歳だったからね。でも、この後、もっと大きなアフロになったんだ。
PJ:オレのはもっとボサボサだったね。それはともかく、オレたちのショウはリズムが正確で、メロディがしっかりしていて、とにかく最高の75分間が楽しめるんだ。
聡一:それは楽しみです! 僕はバンドでギターを弾いていて、おふたりもすごく尊敬しています。
PJ:おお、ギタリストなんだね! どうもありがとう。
RP:ここにはギタリストがたくさんいるな(笑)!
聡一:ライブでプレイするとき、いちばん大切にしていることは何ですか。
PJ:ウーン、何だろう。レイ、答えてくれよ。
RP:楽しむことさ。あと、ステージの前にはまず、日本産のウィスキーを飲むことだな。ほんの少しだけね(笑)。冗談はともかく、とにかく気持ち良く、楽しむことだよ。僕らが考えているのは、ただステージに出て楽しむことだけなんだ。全ての準備は家でやってきたからね。長年にわたって身に付けたことを、自然に表現しているんだ。
PJ:ショウの後で、「いとも簡単にやっているみたいだね」って言われるけれど、僕らはいとも簡単にやっているような演奏をするために、一生懸命練習してきたんだ。ステージで演奏を楽しむには、家やリハーサルでみっちり練習することが大切だよ。
聡一:プレイヤーとして、お互いにどういう印象をお持ちですか。
RP&PJ:え、コイツのこと(笑)?
RP:彼は素晴らしいプレイヤーだよ。やることなすことすべてが素晴らしい。それは今夜のショウを観てもらえばわかる。自分のパートを自由自在に弾きこなすし、どんな状況でも、誰と一緒にやっても、ぴったりとハマったプレイができるんだ。僕も常にそうありたいと思っている。どんな状況でも、どんな音楽にでもハマれることが大事だよ。
PJ:オレはそれを彼から学んだんだ(笑)。共演する相手が気持ち良くなるような、ツボを押さえた、人の邪魔をしないプレイをすることが肝腎で、オレはそれを彼と一緒にやりながら学んだんだ。
亮輔:僕はベース・プレイヤーなんですけど……。
PJ:ベース・プレイヤーだって? 退場(笑)! 冗談だよ。ゴメンナサイ。バカタレネ(笑)。
亮輔:(笑)。お二人とも、たくさんの素晴らしいプレイヤーと共演なさっていると思いますが、その中でも特に印象深かったのは誰ですか。
RP:スティーヴィー・ワンダーだな。作曲の仕方を教えてくれたこともあったし、若い頃から誰よりも印象的で、20世紀のモーツァルトと言えるぐらいの存在になったからね。
PJ:そうだね。オレにとって印象深い人はふたりいる。ホイットニー・ヒューストンとジョージ・デュークだ。ホイットニー・ヒューストンの『Greatest Love Of All』や『Saving All My Love For You』『Where Do Broken Hearts Go』いったヒット曲のレコーディングにも参加したけれど、一緒にツアーをしてステージで彼女の歌を聴いたとき、楽器としての彼女の声は、ほかに類を見ないものだった。ただ彼女が歌っているのを聴くだけでも、信じられないような経験だったね。ジョージ・デュークには、常に自分の限界を押し広げる努力をして、成長し続けるように励まされた。彼が書いた『Bus Tours』という曲があって、これはオレにとって、それまでプレイしたなかでも最高の難曲だった。それで「こんな曲、弾けないよ」と言ったら「いや、弾ける。家で練習して、明日また来い」。
RP:明日また来いって(笑)!
PJ:それで、オレも曲を覚えてプレイしたけれど、彼はそうやって、常に励ましてくれたんだ。
RP:彼はホイットニー・ヒューストンの『Greatest~』に参加したけれど、オレはその数年前にジョージ・ベンソンのオリジナル・バージョンに参加しているんだ。
亮輔:ジョージ・デュークは最後の来日公演を観ましたが、素晴らしかったですね。
PJ:ああ、とにかく最高のミュージシャンだったからね。
貴秋:スティーヴィー・ワンダーについての話と言えば、レイさんが彼から自分のバンドで演奏してほしいと電話がかかってきたとき、ウソだと思って電話を切ってしまったという話を都市伝説的に聞いたことがあるんですが……。
RP:ああ、ほんとうだよ。彼の『Music From My Mind』は、あらゆるアルバムの中で最高だと思っていて、カーステレオでいつも聴いていた。だから、それを知っていた友達の誰かが、オレを引っかけようとしていると思ったんだ(笑)。でも、彼は何度もかけてきて……。
貴秋:1回だけじゃなかったんですか。
RP:1回どころか、3、4回ぐらい。3度目ぐらいには、汚い言葉まで吐いて切っちゃったからね(笑)。それでもまたかかってきて、「僕は本物のスティーヴィー・ワンダーだ。電話を切る前にこれを聴いてくれ」と言って、『Superstition』のリズムトラックだけのものを聴かせてくれた。それでも、出だしのドラムが高校生の叩いているみたいな音だったから、電話を切ろうとしたんだよ。でも、それに続くパートを聴いたら、「うわあ、本物のスティーヴィー・ワンダーだ! ごめんなさーい!」って感じだったよ(笑)。
PJ:それを聞いてホッとしたよ。オレも、おふくろがマイケル・ジャクソンの電話を切っちゃったことがあったからね。
貴秋:ほんとですか!
PJ:ああ。マイケル・ジャクソンから、セッションに参加してくれっていう電話があったんだ。その頃オレはまだ両親の家に住んでいて、電話を取ったおふくろが(マイケルの声色で)「どうも、ポールはいますか? マイケル・ジャクソンですが」という声を聴いて、「あんたね、いたずらはやめなさい!」って切っちゃった(笑)。
RP:これで、大スターから来た電話を切ったギタリストの話がふたつになったな(笑)。
貴秋:すごすぎる話……。そろそろ時間のようなので、最後の質問なんですが……。
PJ:ダイジョウブ(笑)!
貴秋:ありがとうございます。では、あなたにとってファンキーとは何でしょうか?
RP:オレは、“ファンク”という言葉を創ったのはジョージ・クリントンだと考えている。彼以前にファンクという言葉はなかったんだ。それはともかく、“ファンク”というのはある種の感覚(フィール)で、ブラックミュージックに限ったものじゃない。ある種の気持ち良い感覚をつかむことが肝腎で、“ファンキー”な演奏には、それが感じられるはずなんだ。全員がある領域で一体化しているのがね。そこから外れてしまうと、ファンキーじゃなくなるんだ。
PJ:レイはデトロイトの出身だから、ファンクと言えばジョージ・クリントンということになるけれど、カリフォルニアの出身のオレにとっては、ファンクと言えばスライ&ザ・ファミリー・ストーンなんだ。
貴秋:おぉ。
PJ:でも、理由は同じだよ。全員が一体化して、催眠術的な効果を持ったフィールを生み出すことが大事なんだ。肌の色が黒だろうが白だろうが黄だろうが青だろうが緑だろうが、そんなことは関係ない。全員がひとつの楽器のようになって生み出すフィールがファンクなんだ。それを外したらもう、ファンキーじゃない。
RP:あと、「オレはファンキーなんだ!」という自信も必要だよ。
貴秋:よくわかりました! どうもありがとうございました!
【おまけ】