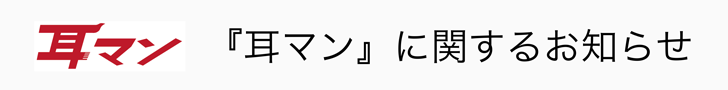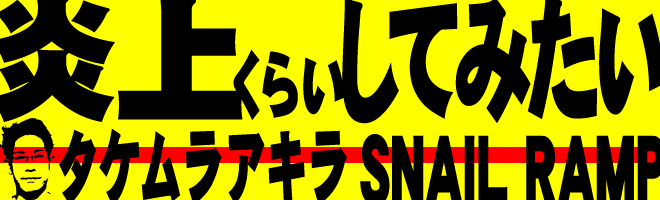「SNAIL RAMPの作り方:その4」タケムラ アキラ(SNAIL RAMP)『炎上くらいしてみたい』
1990年代後半から2000年代のバンドシーンを牽引したSNAIL RAMPのフロントマン・タケムラ アキラが書きたいことを超ダラダラ綴っていく新連載!
アメリカから帰国して(と言うとカッコよく聞こえると思って使った、あざとい俺)、しばらくはまたダラダラとする日々を洋二郎と送っていた。そんな日常のなかで洋二郎は「竹ちゃん、俺またアメリカ行こうと思って」と話し出した。
「ん?」と思ったが、こちらが言葉を発する前に「だからバンドは別々にやろう」と告げられた。「うっそ!!」と驚愕したが、バレないよう「そっか。わかったよ」と素っ気なく答えた。そうしたつもりだったが、実際はどう見えていたのだろうか。ひとりで帰宅する車中、俺はメチャクチャに凹んでいた。
「ひとりになっちゃったな……」
24歳だった俺はいい大人にもかかわらず、とんでもない孤独感を噛み殺しながら、自宅へ辿り着いた。そしてベッドに寝転びながら「うわー、ひとりになっちゃったよ」と、その現実と闘っていた。しかし寝転んでいるだけのクセに「闘っていた」とか言っちゃうのが、バンドマンのバンドマンたる所以だと今更ながら思う。
おまけに「ハァ~、これからは全部自分でやらないといけないのか」と何ともぐうたらな諦観さえ覚え始めていた。このとき俺は24歳、1995年当時のバンドマン界隈では「25歳までにバンド成功の兆しががなければ就職」といった雰囲気があった。そのタイムリミットまではたった数ヵ月。でも今からメンバー集めて曲を書き、押っ取り刀で活動を始めたところでダメに決まっている。
「バンドは諦めるか……」と何回も思った。でもそうやってウジウジと考えている自分は、やはりバンドがやりたいのだともハッキリ気づいた。
俺はここでひとつの決めごとをする。
「最後にあとひとつだけバンドをやってみて、どうにもならないようならバンドは諦めよう」
さっきまで寝転んではいたが、そう決めたら早かった。まずはPUNK系の音楽誌である『DOLL MAGAZINE(現在は廃刊)』のメン募欄(メンバー募集欄)に載せるべく「Vo,G,Dr,を募集。又はBで加入希望。メロディックやSKA調としたパンクをやりたい」と掲載原稿を書き始めた。
ちなみに1994年~1995年当時のメン募は自分の住所、電話番号、氏名もすべて紙面に掲載し、応募者はそれを見て連絡をしてくる。現在のように「個人情報が」という観念自体が存在しなかった。
そしてそのメン募の最後には「UNDER GROUND志向 不可」とも書いた。しかし「とにかく売れたい!!」と思ってたわけではない。漠然と「多少は売れて、バンドマンとして認めてはもらいたい」意識はあったが、あまりに自分をネジ曲げてその結果売れたとしても長続きするとは思えなかったし、売れそうだったのにネジ曲げてしまったがために、失敗したバンドも見てきた。
でも、なぜUNDER GROUND志向が不可だったのか? 俺がそれまでに知り合ったバンドマンやPUNKSのなかには「テレビなんか絶対出ちゃダメだろ」「雑誌に載るのなんかくだらねぇ。魂を売ってんだよ」と言う奴は多く、「メディアに出てる奴らなんぞFUCKだよ、FUCK!」などと言う奴らもいた。
でもそんな言葉を聞くたびに「俺を含めた君たちは“テレビに出ない”んじゃなくて、“出られない”んだよ」と思っていたし、なにより会話のなかに普通に「FUCK」とか入れてくるのを「薄気味悪いなぁ、そんな言葉を無理して使わなくていいのに」と思って聞いていた。そしてそんな考えの人とバンドを組んだ日にゃあ、高円寺から一生出られない、そんな思いが募っての「UNDER GROUND志向 不可」だった。
しかしながら『DOLL MAGAZINE』という雑誌自体が、世間的に見れば明らかにUNDER GROUNDな雑誌であり、そこに「UNDER GROUND志向 不可」という条件でメン募を載せる俺のやり方は、ファーストフード店でバイトしながら「身体に悪いフライドポテトを喰ってるお前らとは友達になれん!」と店内で言って回るようなモノだった。
ところが変わり者はいるもんで、そのメン募を見て電話を掛けてきたのが何人かいた。とは言え、最後となるかも知れないバンドのメンバーをたった数人のなかから選ぶ気にはなれなかった。いくつかのリハーサルスタジオにもメン募の紙を貼らせてもらってはいたが、そこからの応募はひとつもなかったように思う。
これじゃバンドを組むことすらできない、困ったなぁと思っていたところ、偶然にも新たなメン募システムと出会うこととなる。
これがなかなかに強力なシステムだったのだ。